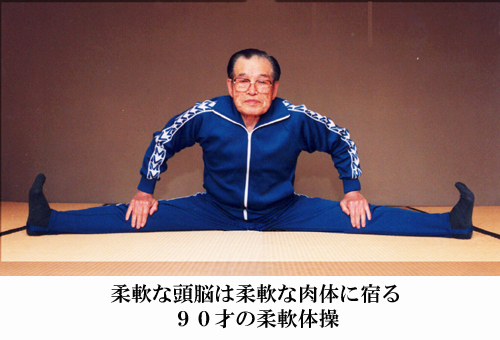大学時代
大学時代
明治43年生まれ、お父上は鹿児島県出身だそうだが氏は江戸っ子である。慶應中学部から野球部で慶應大学へと進む。高松出身の故水原氏とは六大学野球の慶應で三遊間を守った仲である。
のちに天才水原、堅実牧野と言われたこの名コンビも、水原氏は慶應一年からレギュラーとして活躍したが、牧野氏は三年まで補欠であった。
しかし昭和7年と8年にはレギュラーの位置を確保しただけでなく、不断の努力が認められキャプテンを務めている。
当時名監督と言われた腰本監督の信頼を得て、スター選手でない補欠あがりが主将を任されたのだから"亶壇は双葉よりも香ばし"とか、若くして人徳優れていた事が推し量られる。
また六大学野球フアンなら耳にしたことがある、神宮のトラブルとして有名な、早慶戦の『水原りんご事件』の時も慶應の主将として早稲田応援団と交渉し円満に解決を図っている。
牧野氏に野球の話をしてもらうと、当時 氏がレギュラーになってすぐの頃の話をしてくれる。
なかなかレギュラーに成れなかった牧野氏だが大学3年春のリーグの早慶戦に先発メンバーで登場する。守備位置はショートストップ、折悪しくグランドは雨上がりで所々に ぬかるみや小さな水たまりもできている。
『プレイボール』審判の第一声、サイレンが鳴り終わらぬうちに当たりそこないのショートゴロが飛んできた、牧野内野手は突っ込んで前で捕ろうとしたが、足が滑ってドスーンと尻もちをついてしまう。いきなりのエラーに早稲田の応援陣からはヤンやの喝采である。この回はその後をピッチャーが好投して0点に押さえたが、4回の表2アウト二・三塁で次打者の打球は砂を噛むようなショートゴロ、ボールは牧野遊撃手の股間を抜けてセンターへ、まことに見事なトンネルであっという間に2点を失う。
早稲田の応援団からは大歓声、味方の慶應応援席からまでも罵声が浴びせられる。穴があったら入りたいというのはまさにこんなときの言葉、牧野さんはその時、もう孫子の代まで野球は金輪際やらさないぞと思うくらい恥ずかしく惨めな気持ちになったという。その後に更に1点が入って4回迄にスコアは3対0とリードされた。
しかしその裏 慶應にもチャンスがやってくる。
2アウトだが満塁でバッターは9番牧野、その時牧野さんは思った。慶應の代打陣は充実しており自分は非力の9番バッター しかも前の打席では凡退している、そのうえに2つもエラーをしているので、もう代えられるだろうと、ベンチでためらっていた。
ところが腰本監督は『牧野、お前なにをしているんだ!行って打ってこい』と言われた。
今でも思い出すそうだが牧野さんは気を落ち着かせるためにベンチ横の水道の水を、凸凹になって潰れかけたアルミのコップ(チェーンで水道の栓に掛けられていた)でぐっと飲み干してからバッターボックスに向かう。早稲田の投手は左腕の多勢君、鋭いカーブを武器にしているピッチャーだ。苦手のカーブはいやという程練習したが、この前の打席もそのカーブでやられている。今度もカーブが来るだろうと狙っているところへ外へ逃げる球 シュートだ!
思い切ってバットを振るとボールは一直線にライトセンター間ヘ飛んでいく、2塁ベースに滑り込んで塁上にすっくと立った。ランナーは一掃3点が入り同点!
満場は騒然となり慶應応援団はここをせんどと太鼓を打ち鳴らす。
試合はこの同点打がきいて慶應が6対4で勝った。
次の試合でも牧野さんの活躍で5−4と慶應がとり、このシーズンの早慶戦は慶應の勝利となる。
牧野氏は当時を回顧して話す『あの後 腰本監督は知人に=若しあの時、牧野に代えてピンチヒッターを出していたらおそらく牧野は駄目になっていただろう。
責めは自分が負えば良い、彼の一生のことを考えるとたとえ及ばなくても、もう一度全力を尽くすチャンスを与えてやろうと思った。=と仰言ったそうだ。
あの時のヒットが無ければ私は野球とは縁が無くなっていただろうし、今の私は無いかも知れない』と。
トップへ戻る ↑
 社会人野球時代
社会人野球時代
大学卒業後プロからの誘いを断って鐘紡に入る。
水原氏は巨人軍に入団プロ野球選手となる。7年後第2次世界大戦が始まり昭和18年応召され、終戦の翌年(昭和21年)復員。
鐘紡に復帰しオール鐘紡チームを率いる。
当時の都市対抗野球はプロ野球よりはるかに人気があり(オール鐘紡は慶應OB、大昭和製紙が早稲田OB)で固め決勝戦はいつもこの両者で優勝を争うことになったので社会人の早慶戦といわれ、凄い人気であった。
今も同じ黒獅子旗が優勝旗だが、牧野さん率いる当時のオール鐘紡の強さは圧倒的で、昭和25年、26年、27年と3年連続優勝を飾り28年は決勝戦で大昭和製紙に破れ4連覇はならなかったが、翌々年は雪辱を果たし優勝。
都市対抗史上3連覇の記録はいまだなく6年間に4度の優勝はこれからも難しい、オール鐘紡が史上最強のチームと言われる所以である。
『モンテンルパの夜は更けて』
話は変わるが年輩の方は 昭和20年代後半から30年代に一世を風靡した流行歌 渡辺ハマ子の『モンテンルパの夜は更けて』のご記憶があることだろう。
これは当時フイリッピンに第2次世界大戦の戦犯として収監されていた日本の軍人将校(死刑囚も多数)がフイリッピンの牢獄の夜空から遠く母国日本を偲んで詠んだ詩を曲にしたものであるが、哀調のこもったこの歌は広く日本全土の人々に口ずさまれた。戦争の爪痕が痛々しい時期のことである。
そんなとき都市対抗野球の優勝チーム オール鐘紡にフイリッピン遠征の声がかかる。
じつはその前の年にも優勝した オール鐘紡にその話があったのだがフイリッピンの対日感情をかんがみ中止になっていたのである。そのような経緯もあり今度はどうしてもということになる。牧野氏は言う『あのときは2度目の赤紙が来たと思った』と、それほど当時の比国の日本に対する感情は格別に激しく憤りとも言えるものがあった。
フイリッピンに着いた日本チーム全員にホテルからは出ないようにとくに夜間は絶対に外出をしないように・・・ などの注意があったそうだ。
第一戦はたいへんな熱戦で鐘紡チームが延長の末制したが、この時のマニラタイムス(当時 反日報道の急先鋒だったが)の見出しは…。
『吉田首相よ!日比の親善には百人の外交官よりもオール鐘紡のようなチームをよこすことだ!』もちろん記事内容は日本チームへの賛辞である。このことにより一気にフイリッピン国民に好感情が芽生える。
当時の大統領キリノ氏はマラカニアン宮殿に牧野監督を国賓待遇で迎え入れた。
隋伴の朝日新聞記者によると 『荘厳な宮殿の中、いくつもの重い扉を押し開けて奥まったところに大統領の謁見室があった。牧野監督はキリノ大統領に対し充分に敬意を払いながらも臆することなく堂々とした見事な態度で話し合った。そして戦犯に対する一刻も早い釈放をお願いした。
大統領はこの日本の紳士の振舞いに いたく感動されていたという。この年の秋収監されていた戦犯は死刑囚ほかすべて全員釈放となったのである。たくまざるスポーツ外交の素晴らしき勝利であった。
野球界をはじめ世に牧野直隆の名は轟き渡ることとなり、『プロの水原ノンプロの牧野』と監督としても両者並び賞せられることになる。
トップへ戻る ↑
 高校野球連盟で
高校野球連盟で
今から半世紀以上も前昭和12年から高校野球(当時は中等野球)の審判を務めるなど永年に亘っていろいろと高校野球発展につくし、中沢氏(初代日本高等学校野球連盟会長)・佐伯達夫氏(第二代会長)を補佐し、1980年佐伯氏の没後、後継会長を務め現在に至る。
平成3年3月、文部省や体協の意向に構わず いち早く朝鮮人学校にも門戸を開くなど思い切った改革でスポーツ界の差別問題解消の道を拓いた。その時の言葉
『規則が受入れを拒むなら 規則を変えるべきだ』
『十年後に垣根が取り払われているのなら 今ここで取り払っても構わない』
<参加が認められた事実はもちろんだが、あの会長の言葉には感動した>という関係者も多い。
また日本人の悲愴感とヒロイズムからくる感傷
−ピッチャーが一人で投げ抜いてこそ−
という考えが投手寿命を縮めるだけでなく、肩を壊し野球を続けられなくなる事を取り上げ未然に防ぐためにも投手複数制を義務づけるなど、<専門医を招いて全国で指導者講習会を開き故障の原因の追及と予防、大会前のレントゲン検査の実施など科学的な対処にも積極的>
『複数の投手を養成して、ゆとりある練習に取り組んでほしい。精神野球も大事だが肉体も大事。今は、精神主義から脱却する転換時期である』
投手の肩だけでなくすべての障害克服に取り組み、スポーツと健康そして全国の野球部員のこと、いつも球児達みんなの立場に立った画期的な指導方針を打ち出す。これら一連の方針は、氏の選手時代の補欠経験や決してスター選手ではないのに、キャプテンという重責を果たした経験があってこそ生まれ出た考えであろう。
また(1995年1月17日)淡路島・阪神大震災の年の春の選抜高校野球大会を開催するに当たって、被災者に明るい話題と激励のため、そして、この大会のために日夜練習に励んできた選手たちのためにも、開催すべきではあるが、地元被災地からの開催の要望を受けるまで待つという謙虚な姿勢。
そして、ひとたび開催を決定するや否や、復興の妨げにならないための配慮、大型バスの乗り入れ規制、同バス置き場を大阪に確保、応援の自粛など。全く見事に国民的合意を取りつけ、粛々とそして平常と変わらぬ落ち着きのもと大会を成功させたのである。
しかも自宅も被災しており、奥様を横浜の娘さんのお宅に非難させ単身赴任者も顔負けの、一人暮らしを敢行、阪神ホテルに40日間も泊まり込みで大会の準備をこなすという、とても84才とは思えぬ超人ぶりであった。マスコミでも語られることのなかった大会成功の会長秘話である。
野球選手として、また第二次世界大戦は軍人として、戦後は学生野球連盟の一員というだけでなく、企業人としてビジネスをもこなして来られた経験が、困難時に迅速かつグローバルな対応を可能にしたに違いない。